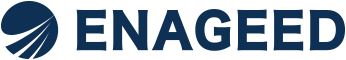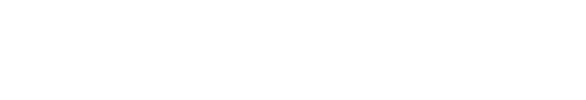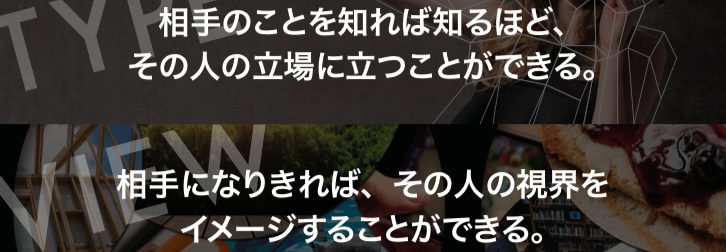
最早、言葉としては市民権を得た「1on1」。
多くの企業で部下の成長支援を目的に取り入れられています。
これまでは半期もしくは年に1回の評価面談でしか生まれていなかった上司と部下のコミュニケーションが、
週1や月1の頻度に変わることで、そのプラスの効果を感じる方々もいらっしゃるのではないでしょうか。
一方で1on1を「実施することが目的」となってしまっているケースも多く存在し、
場が形骸化した結果として、プラスの効果どころかもともとの「信頼関係の低さ」が
顕在化してしまったという声も多数聞きます。
今回は、改めて1on1をどのように位置付けるべきか、
個人・チームにとって価値あるものにしていくためのヒントをお話したいと想います。
■1on1って結局、何のためにやるの?
1on1のニーズが高まっている背景は以下2点です。
・企業を取り巻く環境:「変化が激しく、正解のない時代(VUCA)」
・働く個人の価値観:「仕事に求める価値観の多様化(ダイバーシティ)」
これまでのように正解が見通しやすく、働く価値観が共通の場合は、目指すゴールとその道のり(プロセス)が変化せずに明確です。
そのために年に1回の振返りサイクルでも十分に想定との乖離を埋めて、対応が可能でした。
しかし、今はそのサイクルでは対応できません。
環境への適応と多様な価値観を生かすために様々なコミュニケーションを頻度高く実施して、組織を変化させていく必要があります。
多様なコミュニケーションの中で「上司-部下」間のやり取りは組織において非常に大きな影響力を持ちます。
退職理由の多くが人間関係であるように、上司と部下の直接のコミュニケーションである
1on1は大きな効果を発揮するのでは?となりニーズが高まっているわけです。
1on1は、
・部下の業務を顧客変化、競合変化の激しい中で、適宜修正して達成支援できる
・また上司も経営方針、戦略がアップデートされた情報を適宜共有し、解離を埋めていける
・部下の価値観、感情を把握することで、その特性を生かせる
という位置付けで非常に重要な施策となっています。
■1on1が失敗する理由
とはいえ、前述した通り実際は1on1がうまくいかないと感じるシーンがあるのではないでしょうか。
・何をこの場で話せばいいのかわらかない
・忙しいのにこの時間で話す必要って何だろうか
・話すのが上辺の会話で終わってしまうなあ
この状況が生まれる原因は「1on1 ≒ 仕事」という捉え方にあると考えています。
今の仕事を超えて未来のキャリアや人となりを知る場で通常業務とかけ離れた場と理解されるとボタンの掛け違いが起こります。
もちろん、リラックスした空気で会話をするのが望ましいですが1on1はあくまで仕事です。
それにも関わらず、場当たり的に実施して以下3点がない「3ナイ状態」のために
効果が生まれにくくなっています。
①話す内容に共通認識がない
②事前の準備をしていない
③アクションを決めない
では、1on1を活かすために、
効果を生まれにくくしている①~③を解決するためにはどうしたらいいのでしょうか?
ヒントを資料にまとめましたので、ご興味ある方は
下記よりお読みください。
御社での1on1がより意味のあるコミュニケーションになっていただけるよ
ご支援させていただけたら幸いです。